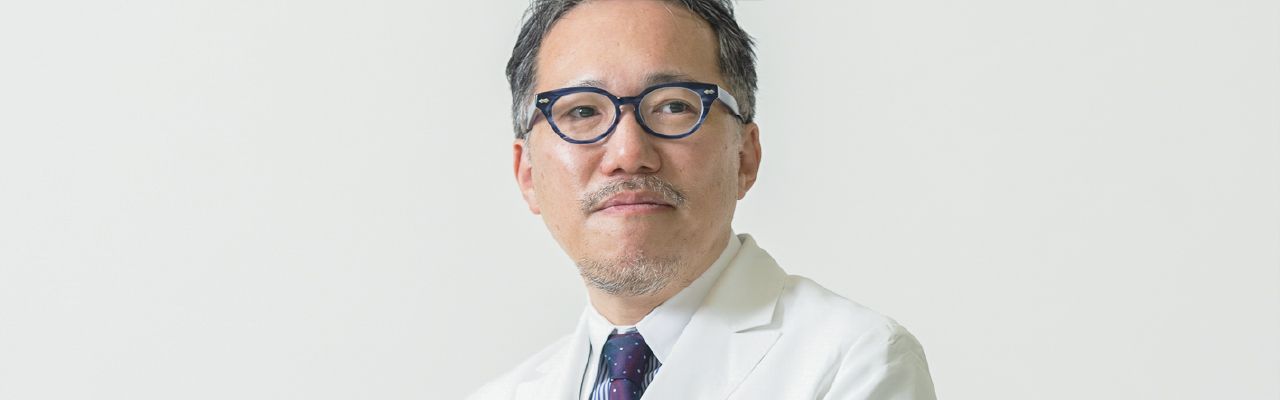「元気な赤ちゃんが生まれて当たり前」と思われているのがお産の世界。しかし実際は緊急事態が起こることもしばしば。私は産科を専門にしていますが、日夜、母児の救急救命を行っているつもりでいます。そして私のライフワークでもある「胎盤・へその緒」の研究を続けているのも、ひとつのお産トラブルがきっかけでした。赤ちゃんとお母さんを繋ぐへその緒は、硬い膠質で守られ、電話線のようなコイル状になっており、赤ちゃんが動いても伸び縮みしやすく、断線しづらい形状になっています。しかし、そのような天与の安全機構を欠くへその緒も時々発生してしまうことがあり、胎児機能不全や胎児死亡となってしまうケースもあるのです。私が経験したトラブルもまさにそうした緊急事態でした。今でもまだまだですが、当時はへその緒や胎盤の状態を詳細に超音波で観察するという考えはありませんでした。臍帯異常は、予測不能であるだけでなく、致命的であるから結果が悪いのはやむを得ないことだと考えられていました。そんな免罪符を使わなくて済むよう、私自身が超音波を使って子宮内の状況を事前に確認する方法を見つけ出そう、と思いました。不足の事態も予知できれば、よりたくさんの命を安全に取りあげられるだろうと考えたのです。

講座|周産期
新たに生まれる命のために、
私たちができる周産期医療。
長谷川 潤一JUNICHI HASEGAWA
大学病院産科副部長、大学病院総合周産期
母子医療センター副センター長、准教授
お産現場の緊急事態を防ぎたい。
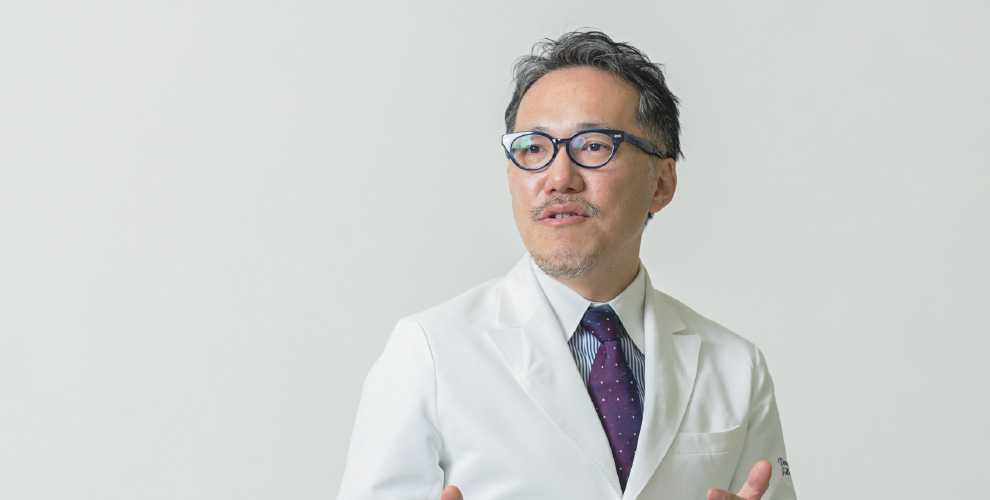

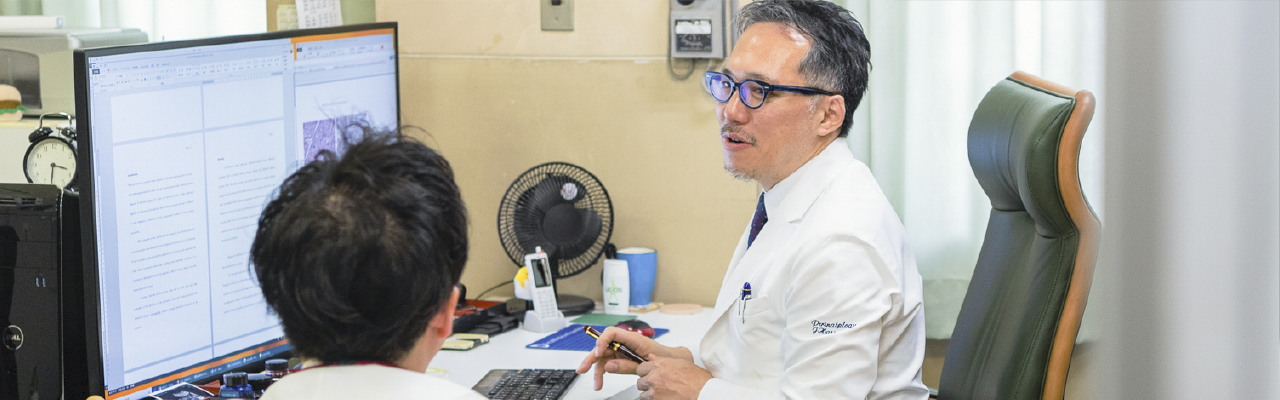
胎内に広がる世界を解明しよう。


ご存知の通り、胎盤とへその緒は赤ちゃんとお母さんにとって非常に重要な役割を担っています。胎盤は母体血から酸素や栄養を送り込み、反対に不要物を外に送り出します。また、ホルモンを分泌することで妊娠状態を維持する役割も果たしています。へその緒は、そんな胎盤と胎児を繋ぐ「命綱」と呼べる存在です。しかし、いまだわからないことも多く、それらを明らかにするため私は日夜研究をしています。超音波を使って、胎盤やへその緒がどのように形成され、成長していくのかを観察したり、胎盤や臍帯の異常はどのように発生し悪影響を引き起こすのかを解明しています。これらは、超音波発生学、超音波病理学などという新しい分野です。もちろん臨床に活かすことにも切磋琢磨しており、世界中の産婦人科医や助産師がいかにシンプルで効率よく健診をするかといった臨床研究、情報を発信しています。より安心安全な妊娠出産ができるように。産科医療はまだまだ可能性に満ち溢れています。
臨床も研究も、経験が実を結ぶ。
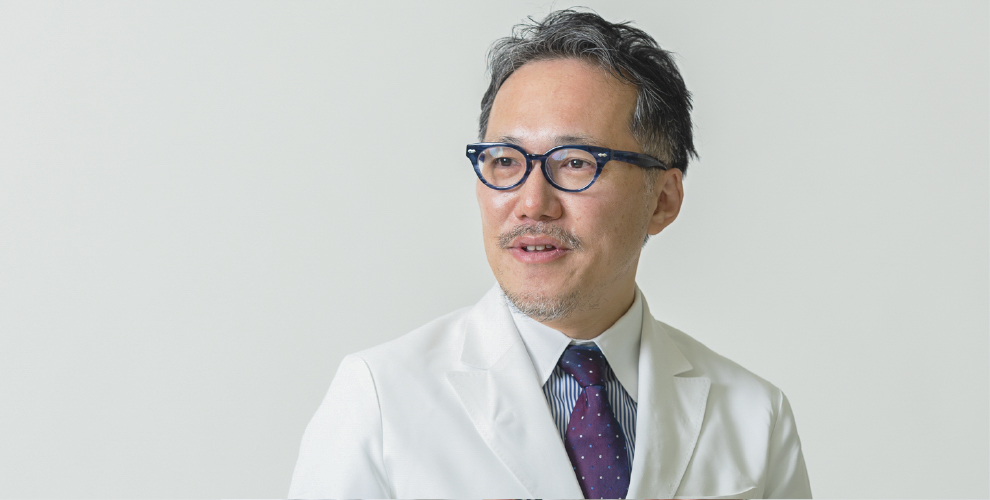
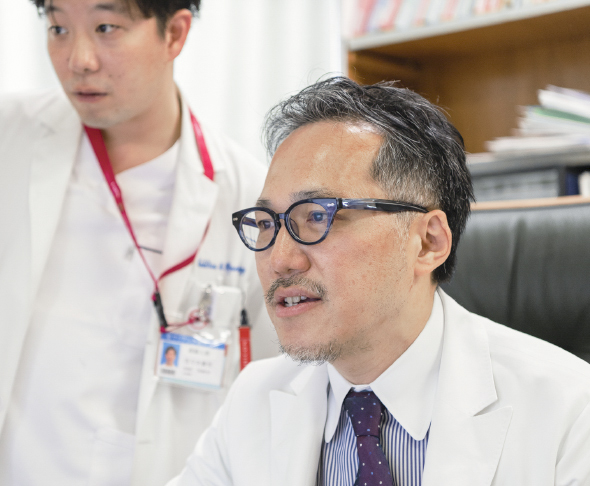
外来ではじめて妊婦さんに出会ってから、健診でコミュニケーションを重ね、自分の手で赤ちゃんを取り上げる。産科の基本的な面白さは、そうした一連の喜びに携われることではないでしょうか。産婦人科は分野が細分化していますが、お産というのは、まず産婦人科医が関わるところであります。経験を培うためには、まずは圧倒的な臨床の経験数を積むことが大事であると考えます。500人ぐらいの赤ちゃんを自分で取り上げてやっとスタートに立てたかなというレベルかもしれません。そのため若手にはとにかく自分でやらせます。患者さんの安全は先輩が担保しつつ、自分の考えるように、信念をもってやってみろと。反省と成功を繰り返して一人前になってほしいと思っています。また、大学病院で働くのであれば、若いうちから自分のやったことをカタチに残すべきだと常々言っています。ですので、積極的に学会発表や論文の執筆などに携わってもらっています。それらは医学の発展にも貢献することにもなりますが、外に自らの意見を発表し、評価され、次を考えるという医師としての基本的な思考回路を身に着けてほしいからです。自分の意見に対する周りからの評価に謙虚なスタンスがないと、独りよがりの医師になってしまいますから。目の前の患者さんはもちろん、より広く、多くの人を救うためにも常に自分たちのやっている医療を見直し、まとめた良い情報を世界に発信していける人材を育てていけると嬉しいですね。
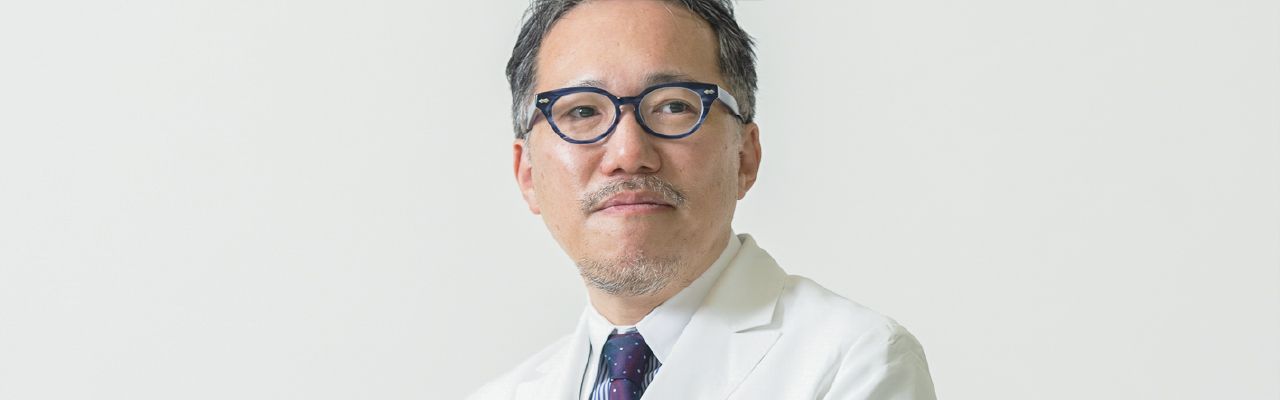
私たちができる周産期医療。
母子医療センター副センター長、准教授
お産現場の緊急事態を防ぎたい。
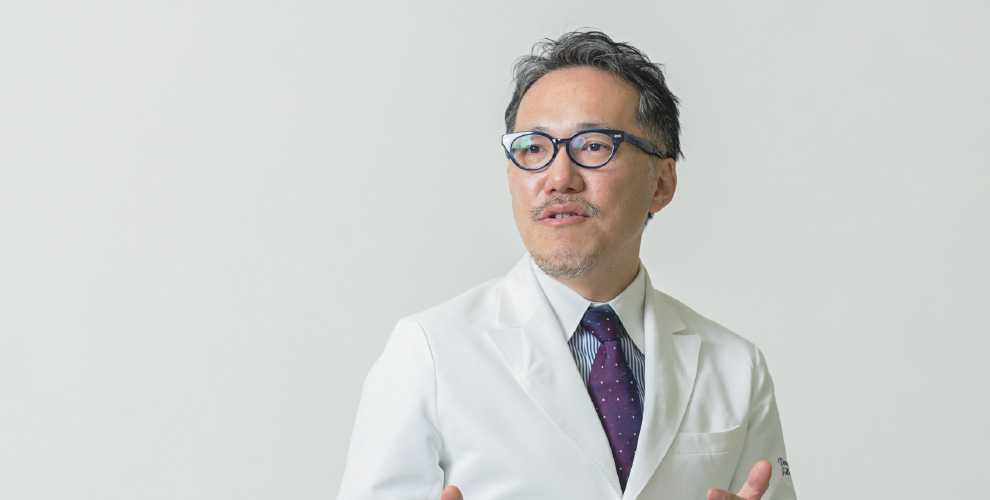

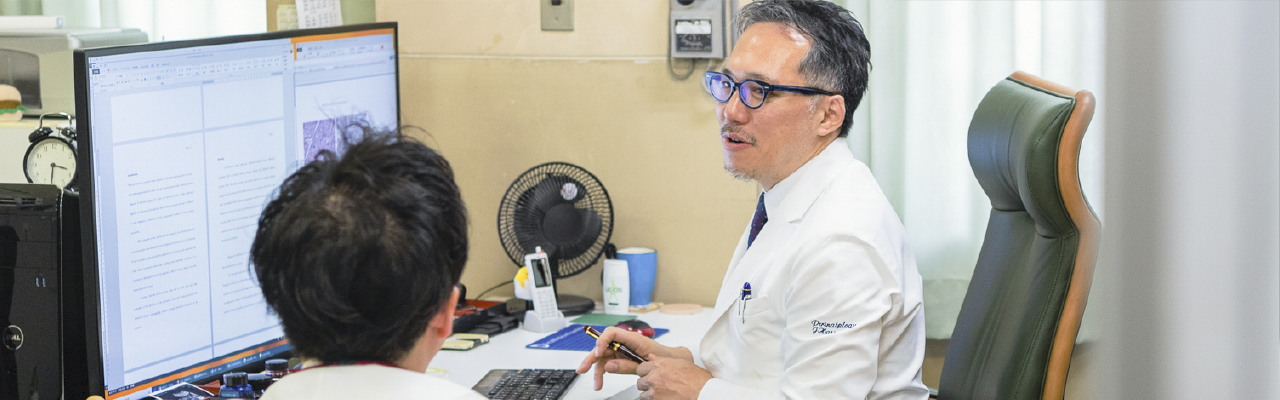
胎内に広がる世界を解明しよう。


ご存知の通り、胎盤とへその緒は赤ちゃんとお母さんにとって非常に重要な役割を担っています。胎盤は母体血から酸素や栄養を送り込み、反対に不要物を外に送り出します。また、ホルモンを分泌することで妊娠状態を維持する役割も果たしています。へその緒は、そんな胎盤と胎児を繋ぐ「命綱」と呼べる存在です。しかし、いまだわからないことも多く、それらを明らかにするため私は日夜研究をしています。超音波を使って、胎盤やへその緒がどのように形成され、成長していくのかを観察したり、胎盤や臍帯の異常はどのように発生し悪影響を引き起こすのかを解明しています。これらは、超音波発生学、超音波病理学などという新しい分野です。もちろん臨床に活かすことにも切磋琢磨しており、世界中の産婦人科医や助産師がいかにシンプルで効率よく健診をするかといった臨床研究、情報を発信しています。より安心安全な妊娠出産ができるように。産科医療はまだまだ可能性に満ち溢れています。
臨床も研究も、経験が実を結ぶ。
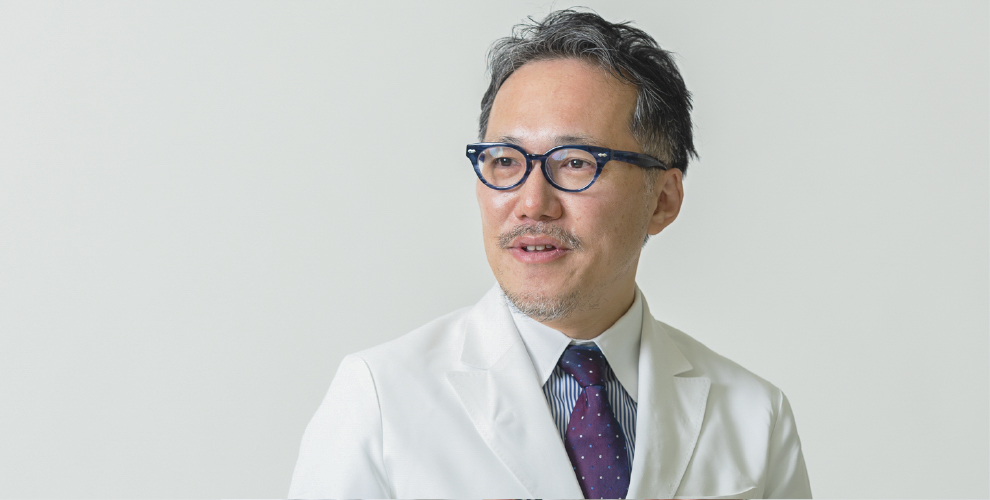
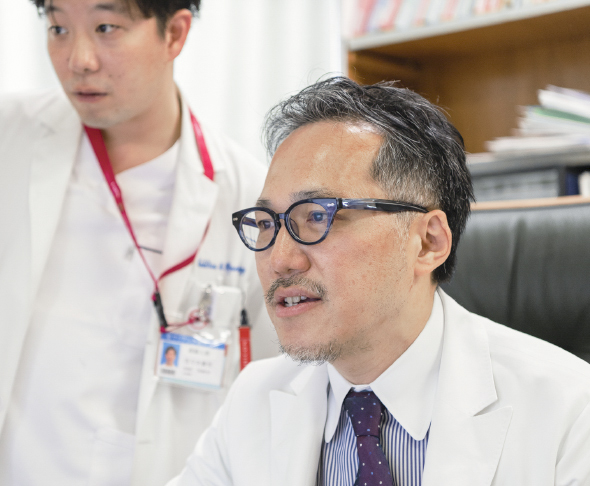
外来ではじめて妊婦さんに出会ってから、健診でコミュニケーションを重ね、自分の手で赤ちゃんを取り上げる。産科の基本的な面白さは、そうした一連の喜びに携われることではないでしょうか。産婦人科は分野が細分化していますが、お産というのは、まず産婦人科医が関わるところであります。経験を培うためには、まずは圧倒的な臨床の経験数を積むことが大事であると考えます。500人ぐらいの赤ちゃんを自分で取り上げてやっとスタートに立てたかなというレベルかもしれません。そのため若手にはとにかく自分でやらせます。患者さんの安全は先輩が担保しつつ、自分の考えるように、信念をもってやってみろと。反省と成功を繰り返して一人前になってほしいと思っています。また、大学病院で働くのであれば、若いうちから自分のやったことをカタチに残すべきだと常々言っています。ですので、積極的に学会発表や論文の執筆などに携わってもらっています。それらは医学の発展にも貢献することにもなりますが、外に自らの意見を発表し、評価され、次を考えるという医師としての基本的な思考回路を身に着けてほしいからです。自分の意見に対する周りからの評価に謙虚なスタンスがないと、独りよがりの医師になってしまいますから。目の前の患者さんはもちろん、より広く、多くの人を救うためにも常に自分たちのやっている医療を見直し、まとめた良い情報を世界に発信していける人材を育てていけると嬉しいですね。